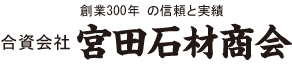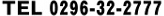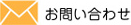|
碑の建立は明治二十七年、今から一二〇年前にさかのぼる。高僧慈教上人の顕彰碑として建てられた。 碑の上部、額部分が佐野常民の書。 |

|
 |
篆書を揮毫した佐野常民 (1822〜1902) 佐賀の七賢人の一人に数えられ 「博覧会男」の異名を持つ |
 |
優美な篆書の筆を残した額部分。 佐野の各方面にわたる造詣の深さを物語る。 |

碑の建立は明治二十七年、今から一二〇年前にさかのぼる。高僧慈教上人の顕彰碑として建てられた。 碑の上部、額部分が佐野常民の書。 |
 篆書を揮毫した佐野常民 (1822〜1902) 佐賀の七賢人の一人に数えられ 「博覧会男」の異名を持つ  優美な篆書の筆を残した額部分。 佐野の各方面にわたる造詣の深さを物語る。 |
【画面をクリックしてください。拡大画面を見ることができます。】
| 近代日本の黎明期に注がれた才能 | ||
佐野常民は1822年、佐賀藩士の五男として生まれ、10才の時に藩医佐野家の養子となりました。藩校弘道館に学び、その後大阪の緒方洪庵、江戸の伊東玄朴の下で学識を広めます。その分野は漢学、医学、蘭学、物理学、化学、外科術、冶金術等多岐にわたりました。 1853年、佐賀藩精錬方主任を命ぜられ大砲の鋳造に精励し、その二年後には幕府が開設した長崎海軍伝習所に参加。 航海、造船術を身に付けると共にその心には、海軍創設の必要性を強く感じることとなります。 1858年、佐賀藩三重津海軍所で海軍伝習を開始、この地で洋式帆船「晨風丸」、日本初の蒸気船「凌風丸」などを完成させました。 明治維新の前年、藩命によりパリ万国博覧会に佐賀藩団長として参加します。この時佐野はパリに限らず広く西欧諸国の軍事、産業、造船術を視察しています。オランダでは軍艦建造の発注もしました。彼は異国の地で歩みを進めるにつれて、博覧会の重要性に加えて欧米の先進性を強く認識するに至りました。 帰国後の佐野は明治新政府に登用され、兵部省では海軍の創設に尽力、工部省では初代燈台頭に就任し洋式燈台の建設にあたりました。 1872年、博覧会御用掛に就き日本の産業の近代化を目指すべく、日本初の博覧会を湯島聖堂で開催しました。続いて翌年には再び渡欧の機会が訪れます。今度は明治政府の渡欧団責任者としてウィーン万国博覧会へ派遣されました。この際、佐野の発案により国内種々の分野から技術集団を万博に参加させ、諸外国の先進技術を習得させました。彼らはその後、おおいに日本の近代化に向け活躍する姿を見せるに至りました。 博覧会を通じて明治日本の躍進に貢献した佐野常民は「博覧会男」の異名を得ています。また在欧の折、国際赤十字社の組織と活動に触れたことは、彼のその後の人生に大きな影響を与えることとなりました。 | ||
| 日本赤十字社ことはじめ =救護団体「博愛社」からの出発= |
1877年、最大最後の士族反乱である西南戦争が勃発しました。その惨状に心を痛めた佐野はヨーロッパで身に付けた知識を基に行動をとります。 「敵、味方の区別なく戦傷者を救護したい」との願いから「博愛社設立請願書」を岩倉具視に提出します。 ところが政府側の認識不足により不許可となってしまいました。佐野はあきらめず戦地本営の熊本にある征討大総督有栖川宮熾仁親王に願い出て勅許を得るや、負傷兵の救護に動き出しました。これが日本における赤十字事業の始まりです。 十年後、博愛社は日本赤十字社と改称し、佐野常民が初代社長に就任しました。 前年には既に万国赤十字条約(ジュネーブ条約)に加盟し、日本の国際的地位の足がかりを作っています。 百数十年を経た現在、大きく発展した赤十字社の組織と活動を見ると、彼が蒔いた種がいかに大切な一粒であったかが理解できます。 |
  西南戦争における博愛社の救護所。日の丸の下に一を加えたマークを社標とした。   佐賀県佐賀市にある佐野常民記念館。 郷土の偉人に対する誇りと敬愛の念の深さが、立派な建物から伝わってくる。 |
|
佐野は晩年、次の言葉を残しています。 文明の発達には精神の向上が不可欠である点を、日本赤十字社を証として説いています。 文明といい開化といえば、人みな、すぐに法律の完備、または器械の精巧等をもって、これを証すといえども、余は独り赤十字社のかくの如き盛大にいたりしをもって、これが証左となさんとするなり。真正の文明は道徳的行動の進歩と相伴わざるべからず 彼の目は、人を射るかのような鋭い輝きを老境に至るまで保っていたそうです。また自身が信じる道は、大泣きしながらも熱弁を奮う、熱き男であったと伝えられています。 佐野常民が篆額を揮毫した「慈教上人之碑」は結城市小塙の満蔵院内に建っています。 施工は当社先祖、宮田九鶴です。 |
| 略年譜 |
| 元号(西暦) | 年齢 | 事項 |
|---|---|---|
| 文政5年(1822) | 0歳 | 12月28日佐賀郡早津江で佐賀藩士下村充贇(みつよし)の五男として生まれる。幼名 鱗三郎。 |
| 4年(1833) | 11歳 | 親戚で藩医の佐野常徴(孺仙)の養子となり、旧藩主齊直から榮壽の名を賜る。 |
| 弘化元年(1844) | 22歳 | 佐賀藩、火術方を設け、砲術研究を始める。 |
| 3年(1846) | 28歳 | 京都で広瀬元恭の塾に入門、蘭学・医学を学ぶ。 |
| 嘉永元年(1848) | 26歳 | 大阪で緒方洪庵の塾に入門。 |
| 3年(1850) | 28歳 | 江戸に転学、伊東玄朴の塾 象先堂(しょうせんどう)に入門。 佐賀藩、築地(ついぢ)に反射炉を建設。翌年、大砲鋳造に成功。 |
| 安政2年(1855) | 33歳 | 6月、長崎で海軍伝習開始(オランダ国王、スームピング号を幕府に献上)。8月、国産初の蒸気船・蒸気機関車雛型を完成。 |
| 4年(1857) | 35歳 | 常民、佐賀藩海軍創設建白書を藩主鍋島直正に提出。 10月、オランダから初購入の飛雲丸の船将となる。 11月、晨風丸(しんぷうまる)打建式。 |
| 5年(1858) | 36歳 | 三重津に船手稽古所(ふなてけいこしょ)を設置、海軍伝習を開始。晨風丸進水。 10月、オランダから初の蒸気軍船電流丸を購入。 |
| 慶応元年(1865) | 43歳 | 三重津造船所で初の国産蒸気船凌風丸(りょうふうまる)が完成。 |
| 3年(1867) | 45歳 | パリ万国博参加のため3月渡欧(佐野常民・小出千之助・野中元右衛門・深川長右衛門・藤山文一の5名が参加)。 |
| 明治6年(1873) | 51歳 | ウィーン万博事務副総裁として参加のため渡欧。 |
| 8年(1875) | 53歳 | 元老院議官となる。 |
| 10年(1877) | 55歳 | 2月、西南戦争始まる。5月3日、大給恒(おぎゅうゆずる)らと博愛社を創立の許可を得た。 8月、第1回内国勧業博覧会を開催。 |
| 11年(1878) | 56歳 | 博愛社副総長となる。 |
| 12年(1879) | 57歳 | 美術団体龍池会をおこし、会頭となる。 |
| 13年(1880) | 58歳 | 2月28日、大蔵卿となる。6月、内国勧業博覧会副総裁となる。 |
| 15年(1882) | 60歳 | 元老院議長となる。 |
| 20年(1887) | 65歳 | 5月20日、博愛社を日本赤十字社と改称、初代社長となる。華族に列せられ、子爵(ししゃく)を授けられる。 |
| 21年(1888) | 66歳 | 枢密顧問官となる。 |
| 25年(1892) | 70歳 | 日赤中央病院建設。7月14日、農商務大臣となる。 8月8日辞任。 |
| 28年(1895) | 73歳 | 伯爵を授けられる。 |
| 35年(1902) | 80歳 | 1月、駒子夫人歿。10月、日赤創立25周年記念式典で名誉社員となる。12月7日、東京・三年町の自宅で歿。 |
『日本赤十字社 佐賀県支部』HPより一部抜粋

|
◆◇「慈教上人之碑」の碑文は明治を代表する書家、
吉田晩稼が筆を揮いました◇◆ |
 吉田晩稼 (よしだ ばんこう 1830〜1907) 長崎の出身 山縣有明の秘書を務めた後に書法を確立。 明治期の教科書の多くは彼の書体で作成された。 「慈教上人之碑」の碑文揮毫の前年には東京九段、靖国神社入り口の大石標を書いていた。 |