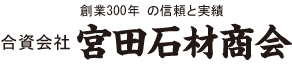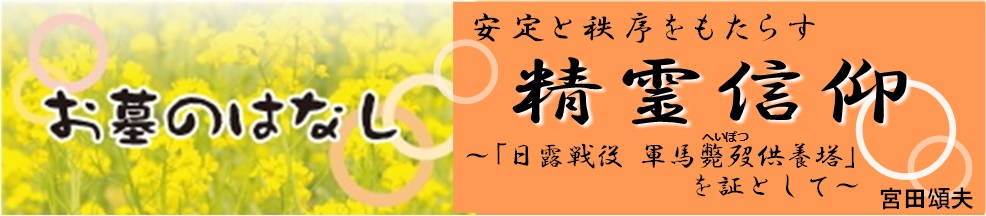

|
|
明治39年(1906)結城市観音町に建立された「明治卅七八年 日露戦役 軍馬斃歿供養塔」。
動物の命も人間同様に大切に扱おうとする気持ちが強く伝わってくる。
自然との共生・生命の連続性を認識する日本人的価値観の現れといえる。
施工は当社です。 |
動物の霊に感謝する日本人
今から120年ほど前、新興近代国家であった日本は大国ロシアと戦火を交えるに至りました。戦闘は1年半続き、我が国の戦死・戦病死者数は9万人と言われています。20世紀最初の総力戦となった日露戦争。日本は明治維新後37年にして国家の存亡を賭けた戦いに直面しました。一般国民も徴用令に従って物資を供出せざるを得ません。殊に馬匹は「戦場の活兵器」として重きを置かれ、国内馬20万頭が徴発を受けて海を渡っています。果たして全国から集められたこれらの馬たちが、戦後どれ程故郷へ戻れたのかは分かりません。 おそらくは過酷な状況下、数多の命が失われたものと思われます。今回掲載の軍馬斃歿供養塔は人間の都合で異国の土となった軍馬を
動物はもちろん草木や人形、裁縫の針など、精霊信仰の対象となるものは数えきれません。いわば日本人は、あらゆる所に存在する精霊によって敬意と感謝の念、時には畏れを抱く感性が磨かれてきたのでした。まさに日本人の誠実さの源流や相手を思いやる優しさ、謙虚さの礎は精霊信仰に求めることができると思います。
折れた針や錆びた針を柔らかい豆腐へ刺し感謝を伝る針供養。
物にさえも命・霊が宿るとする精霊信仰の儀礼のひとつ。


動物を与えてくれた神に感謝する欧米人
世界には様々な宗教・信仰が存在しますが、それらが目指そうとする高みは皆共通しています。すなわち個人の精神的救済と社会秩序の安定を至高の目的としています。ただし、それぞれの教えに即した儀礼や行動・考え方が多種多様であることは周知の通りです。 精霊信仰を基層として、日本人は動物供養を至極当然のように行っていますが、グローバルな視点からするとそれは不可解な行為と見なされています。比較の一例として世界人口比1/3の信者を占めるキリスト教の動物観について触れてみましょう。聖典である『旧約聖書』 第一章 創世記 から神・人・動物の根源的関係性が示された節を抜粋します。- 神は地の獣を種類にしたがい、家畜を種類にしたがい、また地に這うすべての物を種類にしたがって造られた。神は見て、良しとされた。
(25節)
- 神はまた言われた、「われわれのかたちに、われわれにかたどって人を造り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、地のすべての獣と、地のすべての這うものとを治めさせよう」。
(26節)
- 神は自分のかたちに人を創造された。すなわち、神のかたちに創造し、男と女とに創造された。
(27節)
- 神は彼らを祝福して言われた、「生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての生き物とを治めよ」。
(28節)
- ①全ての生き物は神が創造した。
- ②神は神の似姿として人間を造り、これを特別に愛した。
- ③人間は神の委託を受けて動物を管理する。
キリスト教のように高度に体系化された教義を持つ宗教は解釈・論拠が明瞭です。たとえば肉食の習慣に関しても右記のロジックにより正当性が担保されています。つまり動物の命を閉ざして食材とする行為に対しては、言うなれば「神へ対する謝恩システム」を立てることで倫理的問題が生じないのです。
動物の霊の存在を肌で感じている我々からすると、欧米人の動物観はともすると冷たい印象に映ってしまうかもしれません。でも欧米人は彼らが信じるところに依り、適切且つ誠実に動物と向き合っているのです。またその信心を以て古来より合理的に社会秩序を維持してきたことも事実です。「信仰ごとに正義がある」と言われる