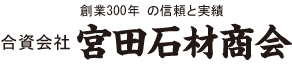|
|
北里柴三郎(1853-1931)。肥後国・現在の熊本県に生まれる。 新千円札の肖像として日々人々の目に触れる存在であるが、この世界的権威の医学博士が、後進の手によって神社に祀られている事実はあまり知られていない。 科学の象徴とされる人物が神格化され、祈りの対象となっていることは、日本人の宗教観を映し出すきわめて興味深い事例である。 |
医学博士 北里柴三郎を祀る社
千円札にその姿が刻まれる北里柴三郎博士は、破傷風やペストをはじめとする感染症の解明と制圧に尽力し、その功績は世界に広く称えられています。純培養や血清療法の確立、さらに研究所の創設など、近代日本医学を世界水準に導いたその歩みは、日本医学史に燦然と刻まれています。また博士は教育者としても多くの後進を育て、公衆衛生や地域医療の発展にも寄与しました。その功績は、医学界にとどまらず日本社会の健康と暮らしに深く根を張るものとなったのです。その北里博士を祀る「コッホ・北里神社」は、東京都港区白金の北里研究所病院敷地内に静かに佇んでいます。時を超えて大学と病院を見守り、静かな祈りの場として人々の心に寄り添ってきました。合理と科学の最前線に祈りの社が共存する姿は、日本人の宗教観の独自のあり方を如実に映し出しています。
師と共に守護神として宿る
この神社の始まりは1910年にさかのぼります。北里博士が恩師ロベルト・コッホ博士の訃報に接し、深い敬慕と感謝の念を込めて建立した「コッホ1931年に北里博士が逝去すると、

コッホ博士と北里博士を祀る社。小さき姿にして、大いなる精神を宿す。毎年6月13日の北里博士の命日には例祭が、5月27日にはコッホ博士をしのぶ献花式が行われ、両博士の遺徳を今日に伝え続けている。合理と精神の融和を体感できる、百余年守られた祈りの場である。
医学と科学の象徴である大学病院に祈りの場が自然に溶け込んでいる光景は、学問と信仰が対立するものではなく、互いを補い合う関係であることを物語っています。訪れる人々がふと足を止め、手を合わせる姿は、科学と精神の調和を体現する日本人の心の在り方を今に伝えています。

ロベルト・コッホ(1843-1910)ドイツの細菌学者で、結核菌の発見により「近代細菌学の祖」と称される偉人。1905年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。1908年には北里柴三郎の招きで来日し、日光や安芸の宮島を巡って日本文化にも触れ、その交流は師弟の結びつきをいっそう深める契機となった。
科学の時代に響く敬虔 の心
先祖や大切な人を祀り、墓や祠を守る姿勢は、今も数多くの家庭に受け継がれています。時代とともに祈りの形は多様化し、新たな選択肢も現れましたが、亡き人の名を刻み、形あるものを前に手を合わせる行為は、人にとって変わらぬ精神の拠り所として尊ばれてきました。
祈る場を持つことは、人と人とのつながりを確かめ、自らの生を省みる大切な契機です。科学や技術がいかに進歩しても、感謝や謙虚さを形に託す習わしは、人間の心を育む源泉であり続けます。
コッホ・北里神社が偉大な医学者を祀り、人々に敬意と感謝を伝えているように、墓もまた祈りの文化を可視化し、世代を超えて精神を養ってきました。神社も墓も、人の心を形に映し出す場であり、科学や合理だけでは語り尽くせない人間の在り方を支えてきたのです。
千円札の顔となった北里博士。その精神が今も息づくこの社は、単なる記念碑ではなく、医学と祈り、人の尊厳と命の重みを伝える特別な場所です。そこには科学と精神が同居する日本的な心が息づいており、私たちに祈りの価値を改めて思い出させてくれます。時代がどのように移ろおうとも、祈りを形に託す行為は人間の本質であり、これからの世代にとっても静かに受け継がれていくことを願わずにはいられません。

東京都港区白金にそびえる北里大学北里研究所病院。その近代医学の拠点の足元に社が静かに佇む。
科学と合理の象徴である病院建築と、祈りの対象としての神社が共存する光景は、異なる営みが不思議に融け合い、日本的精神文化の奥深さを映し出している。